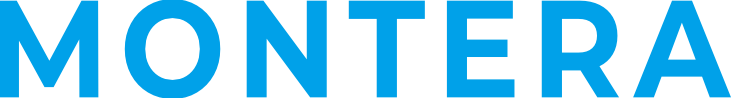新しいシステムやツールを導入したものの、「思ったように使えない」「社員から質問が止まらない」なんて経験、ありませんか?😅そんなIT導入の“つまずきポイント”を実例交えて分かりやすく解説し、トラブルを賢く乗り越えるコツをご紹介します!
1. 🚩 IT導入でよくあるトラブルとその背景
IT導入時によく見られるトラブルには、システムが現場の業務フローに馴染まない、操作に慣れるまで戸惑いが続く、データ移行時の不整合、外部サービスとの連携不良、導入コストの想定外増加などが挙げられます。特に2025年に多いのは、クラウド型業務システム導入での設定ミスやセキュリティ設定の甘さからの情報漏えいリスクです。たとえば、とある事務機器販売会社ではパッケージシステム導入後、顧客対応のオペレーションが複雑化し現場が混乱した、という事例が報告されています。運用現場の声を反映させた要件定義や、設定手順の細かな確認作業を惜しまないことが、トラブル回避の第一歩になります。
2. 🛠️ おさえておきたい事前準備とリスク回避のポイント
ITシステム導入前の事前準備では、現場ごとに業務フローを棚卸し、担当者とディスカッションの場を設けることが重要とされています。IPAや総務省の公式資料では「現場目線での課題抽出」と「役割分担の明確化」が推奨されており、その手順通りに進めた建設業の現場では、紙での情報管理と新システムの併用期間を設けることで混乱が最小限になりました。
- 業務フローの可視化:ホワイトボードや無料ツールで流れを図式化
- 移行計画の作成:段階的なテストや並行稼働のスケジュール策定
- トレーニングの徹底:自社独自のFAQや勉強会も大きな効果
加えて、「初日にすべてを切り替えない」という柔軟な進め方も、現場の混乱を避けるコツとして評価されています。
3. 💬 実際にあった失敗事例と学び
顧客管理システムを初めて導入した食品販売の現場では、細かな業務ヒアリングを省いた結果、現場スタッフの作業手順とシステムの設計に大きなズレが生じてしまいました。そのため、日次報告の二重入力が発生し、業務効率が一時的に低下。この失敗から、本稼働前の「業務フロー実地テスト」やシステム会社との小刻みなレビュー会議が重要であると学ばれています。
- 定期的な現場レビュー:月に一度、小規模なリリースや仕様確認を実施
- 現場主導のトレーニング:管理者以外にも現場主体の勉強会を開催
また、カスタマイズの要望を伝えないまま進めた案件では、業務と合わない機能ばかりが残り、追加費用が発生する事態もありました。
4. 📝 トラブルを未然に防ぐ運用・サポート体制の整え方
トラブルを防ぐ運用・サポート体制の整備では、導入前後の説明会や役割分担表の作成、サポート窓口の一本化が有効とされています。実際に大阪の卸売業では、社内ヘルプデスク担当者を明確にし、社外ベンダーとの連携ルールをドキュメント化することで、障害発生時の対応スピードが大幅に改善しました。
- 社内マニュアルの整備:トラブル時の「対応フロー」をフローチャート化
- 定期的な運用会議:課題・改善点を現場と共有し、記録を残す
- 外部サポート契約の活用:急なトラブルでも電話・チャット対応が可能な体制づくり
自社の規模や文化に合った、カスタマイズ可能なサポート体制が継続的な安定運用につながります。
5. 🤝 トラブル発生時に頼れる外部パートナーの選び方
外部パートナー選びでは、技術力やサポート実績だけでなく「日常対応の柔軟さ」が大きな決め手となります。実際、関東圏の製造業では、24時間体制の障害対応よりも、現場ごとの小さな相談にも快く応じてくれるSIerとの関係性を重視して成果を上げました。
- 担当者変更の少なさ:同じ担当者が長期的に寄り添うことで、微細な課題も把握しやすい
- 現場ヒアリング力:定期訪問やリモート相談会を実施する企業が安心
- 契約内容の透明性:保守範囲や追加見積もりの有無を事前に明確化
単なる「技術サポート」ではなく、現場の日常運用まで寄り添うパートナー選びがトラブル時の安心につながります。
まとめ
IT導入でつまずきを防ぐには、現場のリアルな声を活かした準備と段階的な運用が鍵となります。失敗事例から学び、サポート体制や外部パートナーとの連携も自分たちの業務に合った形で丁寧に整えることで、どんなトラブルにも前向きに対応できます。自分たちの現場に合う工夫を今日から小さく始めてみてください。